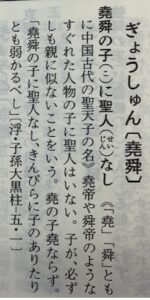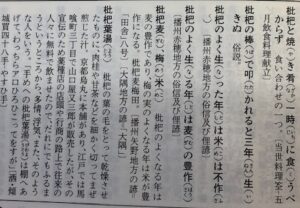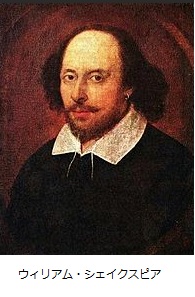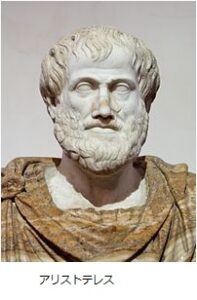男子三日会わざれば刮目して見よ
【読み】だんし みっか あわざれば かつもくして みよ
【意味】日々鍛錬する人が居れば、その人は三日も経つと見違える程成長しているものだ。
【原文】士別三日、即更刮目相待
【読み下し文】「士別れて三日なれば、即ち更に刮目して相待すべし」
【読み】し わかれて みっかなれば すなわち さらに かつもくして あたいすべし
【出典】『三国志演義』
【語源】
三国志の三国の一国、呉の国に、呂蒙という勇猛な武将がいた。
呂蒙は、その無鉄砲とも言える勇猛さで、呉の国はおろか他の二国、魏や蜀にもその名が轟いていた。
その一方呂蒙は無学だったので、君主の孫権が少しは学問を学び、人間の幅を広げるよう呂蒙に諭した。
それから時が流れて、呉の国有数の知将魯粛が、前線司令官として赴任する途中に呂蒙を訪ねた。
呂蒙は、魯粛の赴任先の正面に、当時中国で最強と言われた蜀の関羽将軍が指揮官として居ると聞いて、
関羽の性格を分析し、適切な献策をした。
呂蒙は学問に励み、いつしか勇に智が伴う武将になっていたのだ。
武骨な呂蒙しか知らない魯粛は驚き、
「いつまでも、呉の城下を走り回っていた蒙ちゃんと言う訳ではないなぁ(復た呉下の阿蒙にあらず)」
と笑ったところ、呂蒙は、「士別れて三日なれば刮目して相待すべし」と反論した。
【人物略歴】
〇呂蒙(りょ もう)・・・178年~219年は、中国後漢末期の武将。孫策・孫権に仕えた。
〇魯粛(ろ しゅく)・・・172年~217年は、中国後漢末期の武将・政治家。字は子敬(しけい)。袁術・孫権に仕えた。赤壁の戦いでは降伏派が多い中、主戦論を唱え周瑜と共に開戦を主張した。