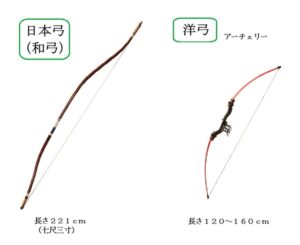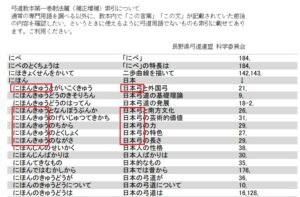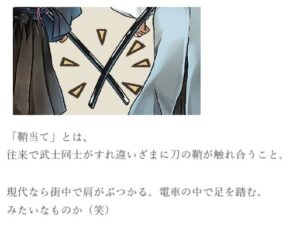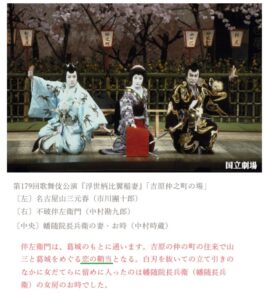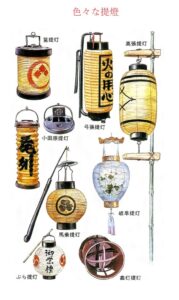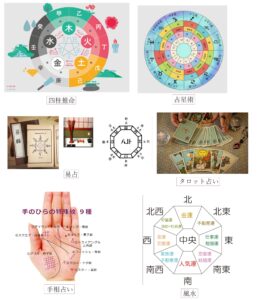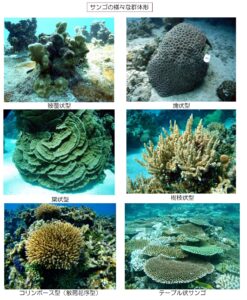捺印
【読み】なつ-いん
【意味】
「押印」と「捺印」と「押捺」は、いずれも判子を押すことだが意味が異なる。
「捺印」は、当用漢字の制定により、「捺」が当用漢字外となった為、「押印」に代用された。よって、「捺印」が由緒ある正統な熟語である(笑)。
ちなみに、漢字の「判子」は当て字。「判子」の正式名称は「印章」ですが、ここでは「判子」で説明します。
「捺印」は、判子を押すことのほか、押した印影についてもいう。
「押捺」は、判子を押すことのほか、指紋を押すこともいう。
一般的に指紋を押すことは少ない為、押捺は殆ど使われない。
ここで言う判子は、苗字だけの同一規格大量生産(例「シャチハタ」)のようなものではなく、木彫りなどで、印影が異なるものを指す。
後者(木彫りなどで印影が異なる)の判子を役所で登録すると実印となる。
実印は、苗字だけでなく名前も彫られた判子を用いることが一般的である。
通常「印鑑」は実印のことである。
「署名捺印」と「記名押印」という組み合わせで用いられる。
一般的、署名(本人が自筆で氏名を書いたもの)に印を押す際は「捺印」と使われる。
本人の自筆ではなく、記名(代筆やゴム印などで氏名を記したもの)に印を押す際は「押印」と使われることが多い。
ちなみに、署名の方が記名より証拠能力が上で、実印を押す場合は、印鑑証明書を添付するのが常識である。
【印鑑の雑学】
〇「印鑑」と「判子」は、一般的には混同して使われるが、次の違いがある。
1.印鑑(いんかん)・・・役所や銀行の台帳に残る朱肉の跡(印影)を指す。具体的には、実印や銀行印のこと。実印の寸法は自治体によって規定されている。一辺が8~25mmの正方形に印影が収まる印鑑とされることが多い。
2.判子(はんこ)(正式名称は「印章」)・・・手に持って押す道具そのものをを指す。実印や銀行印から日常で使う認印もすべて「判子」。前述の通り「判子」と書くのは当て字。
〇実印とは、自治体(市区町村役場)で印鑑登録をした印鑑のことで、個人の場合は苗字だけでなく姓名で作成することが一般的。
法人の場合は、「〇〇株式会社代表取締役之印」などとと記し、重要契約などに使用される代表取締役などの印鑑です。
強い法的効力を持ち、印鑑証明書とセットで求められることが多く、不動産の売買や相続など、重要な契約書に欠かせないものです。
〇銀行印は、取引銀行に登録した判子で、一般的に実印と分けて使う。
〇認印は、苗字だけではあるが、一つ一つ微妙に印影が異なるので、実印に劣るが同一規格大量生産(例「シャチハタ」)などの大量生産されたシャチハタなどに比べて証拠能力がある。
〇実印や銀行印は偽造・悪用のリスクを減らすために複雑な書体が選ばれる。一方で、認印は判読し易いように読みやすい書体が選ばれる。
〇判子は、「はん」「印」「璽」と呼ばれることもあります。
「璽」は飛鳥時代(701年)に制定された大宝律令で、官印(官庁が職務で使う判子)の一つとして天皇御璽が作られたことが始まりです。
現在では天皇のお使いになられる判子だけが「御璽」と呼ばれ、国の判子は「国璽」と呼ばれる。
「御璽」は天皇の国事行為にともなって作られる文書に押され、「国璽」は外交文書など国家の重要文書に押される。
【語源】
〇印鑑の語源は、 「印鑑」という言葉は、判子が本物か偽物かを判断するために、印影の照合に使っていた台帳を「鑑」と呼んでいたことに由来します。
台帳(鑑)には、本物の判子で押した印影が載っており、印影を見比べる道具として使用されていました。そして、いつしか台帳は「印鑑」と呼ばれるようになり、本物の判子で押された印影のことも「印鑑」と呼ぶようになったとされています。
印鑑を照合して判子の真偽を確かめる方法は、今でも銀行などで使われている仕組みです。
〇判子の語源は諸説あります。(前述の通り漢字で「判子」と書くのは当て字)
1.江戸時代によく作られた版画に使う板のことを「版行・板行(はんこう)」と呼び、それが転じて「ハンコ」と呼ばれるようになった。
2.版行(はんこう)を使って書物を印刷することと、印章で捺印することが混同されたので、印章のことも「ハンコ」と呼ぶようになった。
3.「判を押すことを行う」ということばの「判行」が転じて「ハンコ」と呼ばれるようになった。
このように諸説ありますが、真相は不明です。